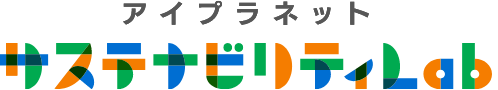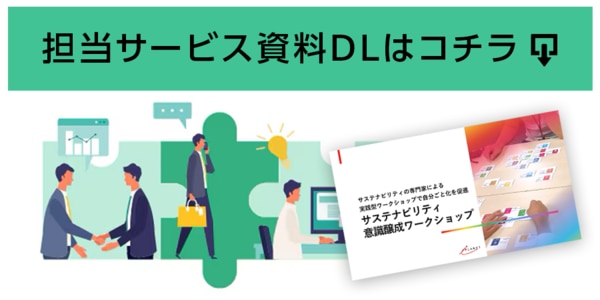【専門家が語る】企業情報の発信時に気をつけるべきSDGsウォッシュ

企業への信頼低下につながるとされる「SDGsウォッシュ」。SDGsウォッシュと指摘されないためには、事業活動はもちろんのこと、コーポレートサイトでの情報発信にも注意が必要です。今回は、アイプラネット サステナビリティLabの共創パートナーであり、地方自治体の本質的な課題解決や機会伸長を支援されている株式会社マッシュアップの亀岡さんにお話を伺いました。

亀岡勇人 共創パートナー
サステナビリティLab 共創パートナー。 株式会社マッシュアップ 代表取締役。 大企業からベンチャー企業まで幅広いクライアントのプロモーション企画を多数手掛ける。主な受賞歴として、日本マーケティング大賞奨励賞、JPMベストプロモーショナル・プログラム賞、電通広告賞銀賞、ACCブロンズ、グッドデザイン賞、日本プロモーション企画コンテスト優秀賞、販促会議インストア動画アワード金賞などを受賞する。 一方、ソーシャルアントレプレナーとして地域活性事業を構想し、地域ブランド開発、関係人口創出、シティプロモーション方針策定など、地方自治体の本質的な課題解決や機会伸長を支援する。 2021年に事業構想大学院大学の特任教授に就任し、地域活性、CSVコミュニケーションデザインなど、ソーシャルインパクトの高い分野の事業開発に取り組んでいる。
SDGsウォッシュの定義とその影響
SDGsウォッシュとは、コーポレートサイトや広告でSDGsに取り組んでいると公表しているのにもかかわらず、実際には取り組んでいない、または公表内容よりも小さい規模でしか行っていないことを指します。
他にも、グリーンウォッシュといわれる環境に配慮しているように見せかけているものや、ピンクウォッシュと言われる LGBT 関連に取り組むといって実際には取り組んでいないもの、ホワイトウォッシュと言われる企業の不正に関連するものなど様々なウォッシュが存在します。
亀岡氏:
環境に良い事業を行っているように見せかけている場合、SDGsを活用して取り組みを発信しているのであれば、SDGsウォッシュとグリーンウォッシュの2つに該当します。SDGsウォッシュに値するかどうかは、企業が「SDGsを使ってブランディングをしているか」がポイントです。
ESG経営など、投資家や一般的な消費者からのサステナブルな取り組みに関する興味は高まっています。そうした背景の中、SDGsウォッシュと指摘されてしまうと、SNS上で炎上して不買運動などが起こると同時に、投資家からの評価も下がることで、企業の価値自体が低下してしまうリスクが存在します。
SDGsウォッシュの事例
では、どのような場合にSDGsウォッシュと指摘されてしまうのでしょうか。
SDGsは、その目標が多岐に渡るがゆえに、多くの分野の不祥事と相関関係を持っています。例えば、ある企業が産地偽装(主に目標12)や人権侵害(主に目標5や10)、環境破壊(主に目標13~15)などを行い、世間から指摘されたとします。この企業がこれらの目標に関する取り組みを行っている旨をコーポレートサイトで発信している場合、SDGsウォッシュでもあると指摘されてしまうケースが増えています。
とある食品メーカーでは、経営者が自動車事故を起こし相手の運転手を恫喝しているシーンがSNS で拡散されました。元々はSDGsに積極的に取り組んでいる企業として高く評価され、多くの就職希望者が集まる企業でしたが、この事件を機に、厳しい働き方や内部事情が暴露され、SDGsウォッシュだという指摘を受けました。結果、就職希望者が減少し、毀損したブランド力を取り戻すのに苦労することになりました。
海外の事例では、商品の原料として使用されるパーム油に関して、環境や人権に配慮してないという指摘がありました。パーム油の生産には広大な土地が必要となります。そのため、インドネシアをはじめとする東南アジアの森林が伐採され、その結果、オランウータンなどの動物たちの生息地が失われ生態系の崩壊を招いています。

また、日本国内の化粧品会社でも化粧品の材料として使用するために購入していたココナッツが、実は野生の猿を違法に飼育し調教を施して収穫させていたものであったため、動物愛護の観点からSDGsを掲げる企業として適切ではないと問題視されました。
コミュニケーション上の落とし穴
情報発信の仕方によって、SDGsウォッシュと指摘されてしまうケースもあります。
●時間の経過とともに誇張表現に変化してしまう
誇張表現には注意が必要です。働き方改革に関する発信では、本社や工場では取り組んでいるものの、営業所や支社レベルは全く実施されていないケースが散見されます。また、発信情報をまとめた時点では取り組んでいたが、時間が経つにつれて規模が縮小していたり、取り組み自体が廃止されたものをそのまま転記してしまうことにも注意が必要です。例を挙げると、とある企業が、過去に1度だけ発展途上国での雇用を生み出す取り組みを行いました。これをサステナビリティページに「途上国における雇用支援」というように表現し、今でも継続して行っているような印象を読み手に与えてしまったことで、SDGsウォッシュだと指摘されたケースもあります。
●明確な根拠を示さずにただ当てはめている
SDGsに何らか関連した事業を行っていると漠然と考えている企業様の場合、17個ある目標すべてに取り組んでいるように見せてしまうのはよくあることです。しかし、明確な根拠がないまま各ゴールのタグ付けをすることは、SDGsウォッシュの指摘につながります。しっかりと数字的な根拠を示すことが重要です。
亀岡氏:
どうしても企業を広報する担当者は、少しでもステークホルダーから良く見られたいという気持ちが強くなりがちです。しかし、目標とやるべきこと、やれていること、いないことをしっかり整理しながら、社内でコミュニケーションを取り世の中に報告をしていくことが大切です。
まとめ:SDGsウォッシュを防ぐには
企業が持続可能な発展を目指すためには、まず目標やSDGsそのものの理解を深めることが重要です。自社が解決すべき社会課題は何かを明確にし、それを解決するために必要なステップをしっかりと考えた上で、具体的な取り組み内容を決定していくことが求められます。
また、Webサイトに掲載する際には、そのステップを明確に表現することと、専門家による確認プロセスが必要です。これにより、企業の取り組みがどのように進行しているのかを客観的な視点も入れて、ステークホルダーに分かりやすく伝えることができ、信頼性を高めることができます。
アイプラネット サステナビリティLabでは、「サステナブルな社会をコミュニケーションのチカラで共に創っていく。」をテーマに、こうした企業のサステナビリティ推進のお手伝いから、プロダクトやサービスへの実装・展開まで、各分野のスペシャリストと共にさまざまな企業活動の伴走支援を行なっております。ぜひお気軽にご相談ください。