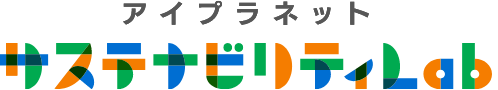健常者と障がい者がともに参加する陸上クラブを主催。 塩家吹雪さんが考える「インクルージョン」とは?
今回のトピックスは、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)です。サステナビリティというと、まず「環境への配慮」を思い浮かべる方が多いかと思いますが、DE&Iの考え方に基づき、企業の内部において多様な価値を認め、受け入れることはとても大切なことです。障がい者の雇用について社会の関心が高まっている昨今、健常者も、障がい者も共にいきいきと働ける職場をつくることは、企業にとって最大の関心事と言っても過言ではありません。
今回のコラムでは、短距離種目の全盲ランナーの伴走者として、世界的な大会で活躍し、健常者と障がい者が一緒に参加する陸上クラブ「シオヤレクリエーションクラブ」を主催なさっている塩家 吹雪(しおや ふぶき)さんをお招きし、塩家さんのスポーツの世界での体験から共生のヒントを探りたいと思います。

右:塩家吹雪さん 左:アイプラネット 村岡
[プロフィール:塩家 吹雪(しおや ふぶき)]

- 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修了(スポーツ科学/修士)
- 障がい者と健常者がともに参加する陸上クラブ「NPO法人シオヤレクリエーションクラブ」 理事長(代表)
- 陸上選手として活躍し現役引退後、短距離種目の全盲ランナーの伴走者として国際大会の
日本代表となり、メダル獲得・入賞などの実績を残す - 日本代表監督やコーチを歴任
目次[非表示]
幼少期・少年時代の逆境と陸上に取り組むきっかけ
村岡:塩家さんが陸上の道に進まれたきっかけからお伺いさせてください。
小学校に上がるぐらいに両親が離婚しまして。1つ違いの弟と二人だけで貧しい生活をしていました。両親の離婚を理由に友達から距離感を空けられることが多く、学校の先生の接し方にも、偏見があったと思います。そんな生活をしていたので、周囲への反発もあり、悪さばかりしていました。
中学で友人に誘われて陸上部に入ったのですが、お金がないからユニフォームが買えない。そこで顧問のO先生に「ユニフォームが買えないから大会に出られません。」って言ったんです。そうしたら「余っているユニフォームがあるから使いなさい。」って言ってくれたんです。そのO先生が、「スポーツの世界では、家庭環境が悪いとか、お金がないとか、そういういろんな条件が悪くても、必ず一番になったら評価が上がって誰にも文句を言わせないような存在になれる。」と仰って、その言葉が、僕の中にすごいズドーンと入ったんです。それで365日、本当に休みなく頑張ったんです。最終的に200mでは東京都5位まで行きました。
高校は陸上の名門、本郷高校に進学。その後も専門学校、社会人と陸上に取り組み、卒業後はリレーで日本選手権に出たり、全日本実業団大会の決勝に行ったりもしました。さらに力がついて全日本の大会とかにも出られるようになったんです。
目に障がいのあるランナーとの出会いと伴走
村岡:障がい者も健常者も一緒の活動をスタートしたきっかけを教えてください。
29歳の時でした。競技場で練習をしていたら一人の選手が走っていて。その横でコーチが手を叩いていた※んです。その選手に「何をやっているんですか」って訊いたら、「僕、実は目に障がいがあります」と。盲膜色素変性症という、だんだん視野がなくなり、最終的に失明してしまう原因不明の難病です。彼を自分のクラブに誘ったのですが、「目が悪くなると皆さんに迷惑かかってしまうから」と辞退されました。「何が迷惑かかるの?」と訊いたところ、紐を持って伴走をしてもらわなければいけなくなるとのこと。「自分も含めて100m10秒台のメンバーが沢山いるから、空いているメンバーで手伝うよ」と話したところ、「じゃあぜひ入れてください」ってなったんです 。健常者のチームに障がい者が加入したのは多分日本初だと思います。これがきっかけとなって義足の選手、車いすの選手など様々な選手が全国から集まってきて、障がい者と健常者が一緒に活動する同好会チームがスタートしたのです。
※目の見えない選手を誘導するため
そんな中、2001年には、カナダの世界陸上エドモントン大会で全盲クラスのエキシビションレースが組まれ、S君という選手からそのレースの伴走者を探して欲しいという話がありました。なかなか上手く息があう伴走者がいなかったのですが、僕がやったら、一発であったのです。それが伴走者としてのキャリアの始まりです。

塩家さん(右)の伴走の様子
障がいは個性
2004年に僕は大きな国際大会で日本代表として伴走し8位入賞したのですが、心臓の病気にかかっていた弟が、その時にペースメーカーを入れたんです。弟は「俺がこういう病状だってことを兄貴に伝えたら、兄貴は競技やめてすぐ帰ってきてしまうから絶対言うな」って周りに言っていたみたいです。
彼は障害者手帳を持っていたのですが、「手帳を持ってから、友達から連絡がなくなった。普通に飲みに行った友達から、『まあ、無理するなよ』とか言われる。俺は全然変わってないのに、この手帳1つあるだけですごく距離感を感じるようになったんだよ。」とこぼしていました。「俺、これ持つとそんなに表舞台に出ちゃいけないの?俺は障がいって個性だと思ってんだよ。だってメガネかけてる人に『なんでメガネかけてるんですか?』って、言わないだろ?」って、心臓の病気で亡くなる前にそう言っていました。健常者も障がい者も一緒の活動に取り組む原動力として、やはり弟の言葉は大きいですね。
本当のインクルーシブとは相互理解。分離することではない。
村岡:塩家さんが考えるインクルーシブな環境とは何かをお聞かせください。
例えば、うちのクラブでリレーをする時、「走るのが苦手な遅い人がいるのなら、速い人がその分カバーすれば勝てるじゃない」って指導するわけです。それは、仕事でも一緒じゃないですか。できるやつはどんどん進んでいけばいい。できない人はできる人に追いつけるように頑張ればいい。できる人とできない人が違う方向を向くんじゃなくて同じ方向を向きながら、できない部分はできる人が補う。だからといってできない人が、できないままにするんじゃなくて、できるように努力すれば両方が上がっていくわけです。これが本来のインクルーシブな形だと思います。
日本のインクルーシブ教育は、「その子に合った指導をする」っていうのが一番問題です。その子に合ったってことは、例えば、視覚障がいだったら、視覚障がいの子ども用の指導をするんですよ。知的障がいだったら、知的障がいの子にあった知的障がいの教育をするんですよ。そうすると健常者とのつながりがなくなるわけです。これを「分離教育」といいます。障がい者が増えたから、支援学校をいっぱい増やすんですよ。むしろ障がい者が増えたんだったら、増えた障がい者を健常者の中に入れて一緒にやっていけばいいのですが、それをやらないから、障がい者側からすれば 「私たちはやってもらって当たり前だ」って気持ちになる。サポートが足りなければ「障がいがあるのになんでやってくれないんだ」と思う。健常者側からすれば「障がい者だからやってもらえていいよな」ってなるわけですよ。

シオヤレクリエーションクラブの皆様
大切なのはお互いをさらけ出すこと
村岡:職場でインクルーシブな環境を実現するためにどんなポイントがありますでしょうか。
大切なのは気を使わないことだと思います。お互いが何ができて何ができないかっていうことを、ちゃんとさらけ出せる環境。多分うちのクラブオリジナルなんだなと思うんですけど、例えば全盲の子がいるじゃないですか。健常者の子がいるじゃないですか。健常者の子が、目の見えない子の目をじっと見ているんです。「何で目が見えないの?」って。これを見るとほとんどの健常者の親は「そんなこと聞くんじゃないの」って慌てて子どもに言いますが、うちはそれをそのままにしておくんです。すると何が起こるかというと、目の見えない子が健常者の子に、自分の障がいについて説明してくれます。そして、目の見えない子のことを理解するんです。うちのクラブでは、健常者の子たちも目の見えない子の手引きが自然とできるようになっていきます。
会社でも、普通に、知的障がいの人や視覚障がいの人と健常者、そこに車椅子の人がいて一緒に食事に行く、飲みに行く、仕事もするっていうようなのが当たり前になっていくことが一番大事なのかなと思いますね。やっぱり、気を使わないでお互いがお互いをさらけ出せる環境が大切です。だから、ここまで言ったら申し訳ないとかっていうことを思わず、言いたいことはしっかり言える環境、障がい者でも健常者でも言いたいことはしっかり言える関係が一番かなと思います。
やはりお互いを良く知ることに尽きる
村岡:現状では、障がい者と上手くコミュニケーションが取れるか不安に思っているビジネス
パーソンもいらっしゃると思います。塩家さんから何かアドバイスがあればお願いします。
一緒にいる時間を長くしてこの人はどういうものが好きでどういうものが嫌いだとか知ることが大切だと思います。友達ってそういうのあるじゃないですか。「ごめん、魚食べられないんだ」とか、「こういうものが嫌いなんだ」とかって知ることも大切だと思います。障がい者っていう目線になると、多分そこまで話している人は圧倒的に少ないんですよ。もっと深くなったらいいと思いますよ。浅めの付き合いじゃなくて、気を使わない関係をつくるのにも、とにかく一緒に関わる機会がたくさんあるのが一番じゃないですかね。
スポーツ以外の場でも情報発信を
村岡:シオヤレクリエーションクラブの今後の活動についてお聞かせください。
秋口から関西のジュニア教室を始める予定があります。また専門学校の非常勤講師も務めます。ホテルスクールのような学校で、「お客さんで杖をついている人が来たらどう対応するのか」、「車いすの人が来たらどうするのか」などの授業をします。大学などの教育機関から非常勤などの話も多くなってきました。今まではスポーツ領域だけだったんですけど、教育の場等にもしっかり発信できる機会が多くなってきました。それも含め広く浅くいろんな人と一緒に活動することは、今後の日本全体を変えるレベルの大きなものになっていくことだと僕は思っています。なので、スポーツ以外の分野でも発信する機会を増やしていきたいなと思っています。
困っている人を助けてあげられるように。みんな同じという
意識を持てるように。
村岡:塩家さんと一緒に活動をしてその考え方を共有した人に期待する行動は何でしょうか?
障がいを持った人が困っている時に、必ず何でもいいから声をかけるように。困っている人がいた時に助けられるような、そういう目を持ってもらいたいと思います。あとは自分の周りに障がいを持っている人がいた時に「みんな同じなんだ」っていう目を向け、今までとは違った対応ができるかどうかを考えて行動する。そういうことを一つの新しい訓練だと思ってやってみて欲しいと思います。
村岡:塩家さん有難うございました。
今回は、塩家吹雪さんから、共生を実現する上での意識、「お互いを理解し、お互いを認め合い、補い合うこと」の大切さをお伺いしました。このコラムが皆様の社内のDE&I推進の一助となれば幸いです。